
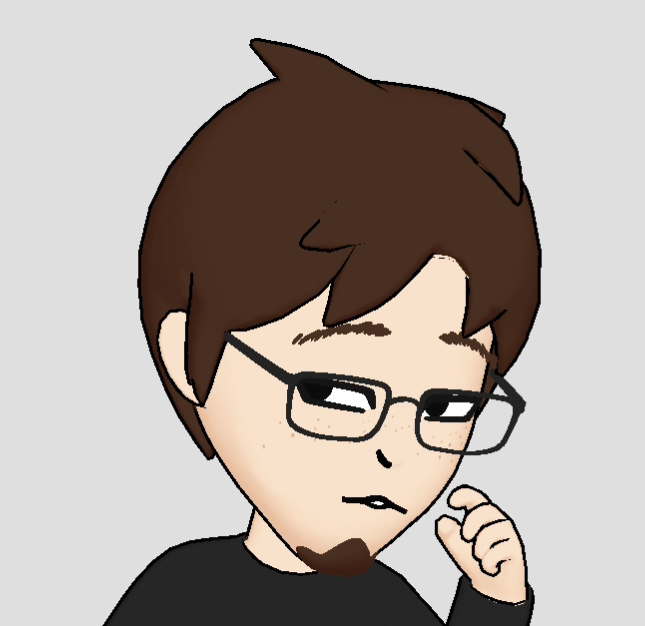
プリンター買ったけどどこに置こうか・・・
ついでに収納も増やしたい
ということで・・・
普段作業で使うものも収納できる
『ツールワゴン風のプリンター台』を作ってみました!
ドンッ!

作業ポイント
✔3色カラーで部屋に置いてもクールな配色
✔接合部が見え辛い設計にチャレンジ
◆作業風景
完成した見た目はただの棚だけど、なんだかんだで苦労したし時間もかかってしまいました。
自分でゼロからつくるって難しい。改めて痛感ですね。
◆購入または準備したものリスト
⇒「使用部位」 「材料名・商品名称」 「サイズ」 「個数」 の順番
- 棚板 1×4材 6ft 4枚
- フレーム 2×2材 6ft(2本) 3ft(1本)
- 2×4材―3ft 1本
- キャスター―自在2つ、固定2つ
- 桧材―幅25㎜×厚さ15㎜×長さ900㎜
- 塗料(天板) 水性ウレタンニス(和信ペイント) 色:ローズ
- 塗料(棚板) ワトコオイル 色:ダークウォルナット

作製費 3,000円(塗料代除く)
手順1.材料を加工して準備する
今回使用した材料は全て「1×~」「2×~」といった規格の製品です。
これらは比較的安く購入できるので材料コストを削減できていいですよね。
<各部品ごとの使用材料>
骨組み:2×2材
棚板・天板:1×4材
他の材料の選択肢・・・
フレーム部分の材料では、ひとまわり太めの2×3材の採用も考えていました。
しかし、少しでも細い方が部屋に置いた時の圧迫感も軽減されスマートな印象になると思ったので2×2材を採用しました。

手順2.それぞれの部位を作製する
「フレーム」「棚板」などのパーツを作製します。
骨組みの作製では”組み手”っぽいことにチャレンジしました。
■フレームの作製~組み手の練習をしました
今まではビス止めで接合する方法しか実践してきませんでした。
今回は”組み手”の練習の兼ねて下手くそながら挑戦してみました。
Q.組み手とは?
ー板に凹凸や段などの加工を施した板通しを「手をつなぐように」組み合わせた手法。
難易度は高いが、接合部の強度がかなり上がる


これを組み手と呼べるのだろうか・・・
簡単そうな構造なのにすごく手間がかかるわ。
強度は上がってるかもしれないけど、
僕の場合、ネジ頭も見えてしまっているから見た目が悪いよな。

<私が行った組み手の方法>
使用した道具:ノコギリ、ノミ
- くり抜く部分に寸法線を書く
- ノコギリで大部分カットする
- ノミで正確に寸法で削る
- ペーパーやすりで仕上げる



最後に棚受けとなる角材を取り付けました。
■すのこ式の棚板の作製する
カットした1×4材を並べてウラから角材を張り付けました。
こうして写真で見ると見栄えが悪いのですが、
ウラになって接合部が隠れるので大丈夫。

手順3.塗装~オイルフィニッシュと水性ウレタンニスを使用
天板:水性ウレタンニスのローズ(信和ペイント)
棚板:ワトコオイルのダークウォルナット
骨組み:水性塗料のつや消しブラック(信和ペイント)


黒のフレームとダークウォルナットのワトコオイルが相性抜群!
■初挑戦『オイルフィニッシュ!』
木目を生かしてアンティークっぽく仕上げるならオイルフィニッシュ!
いろんな方の作品を見ているとよく目にしていたので、マネしてやってみました。

<ワトコオイルの使用方法>
①塗装面をサンドペーパーで磨く
②布や専用の筆で適度に塗って延ばす
③30分くらい乾かしたら①②を繰り返す
④最後に布で拭き取る
⑤1日以上乾燥させる
大体こんな感じでした。
普段僕が使っている水性塗料などと比べると若干手間がかかるし、乾燥させる時間も長くなってしまいますが、そんなに違いがあるものなのか、果たして・・・・

正直言って、かなり好感触!
もっと早く知っておけばよかった!
今まで使用してきた水性塗装は、塗り方や塗料の種類・メーカーによって木目が消えたり残ったり様々でした。
しかし、オイルフィニッシュだと確実に木目調が浮き出て、それほど塗り方にも左右されず自然な木材の風味が生かされているように感じました。
■水性ウレタンニスの重ね塗り経過記録
水性ウレタンニスは、塗料を何度も重ねることで効果を発揮します。
それに伴い、色合いも濃くなり重厚感が増すように変化します。
その変化を写真でご覧ください。

ー重ね塗りごとの色の変化




塗料を重ねるにつれて色が濃くなっているのがわかりますよね?
また、ウレタンの膜も層になって厚くなるので、材料の保護性能もアップし
さらに艶やかになりました。
ジョイントテーブルと同じく、水性ウレタンニスで塗装した
⇒ジョイントテーブル作業レポートへ
手順4.組み立てる
既に手順3で完成写真を載せていました。
組み立てた順番は次のような流れで行いました。
- 下段から順に2つのフレームと接合する
- 幕板を取り付ける
- 天板をビス止め(オモテ面から)
- キャスター取り付ける
なんかわかりにくいけどこんな感じ💡
完成!


実際に使用した様子

技術的にはまだまだまだまだだけど、
完成して塗装してみると結構カッコよく出来上がりました!
意外にこういう家具って店頭に置いてないから、自分で作れてよかったですね!
【主な購入品紹介】
お気に入りの作品に味わい深さを『ワトコオイル』
 | ワトコオイル 200ml WATOCO 油性塗料 木部用塗料 オイルフィニッシュ オイルステイン ダニッシュオイル 木材専用 木材着色 DIY 亜麻仁油 価格:1,540円 |
 | ニッペホームプロダクツ ワトコオイル 1L 全7色 WATCO 木材専用オイルフィニッシュ DIY 屋内木部用 価格:2,890円 |
木目調をより際立たせてくれる『ワトコオイル』
私の場合、オイルフィニッシュ自体難しそうでかなり敬遠しがちでしたが、水性塗料とほとんど同じ要領で塗装してもしっかり着色し、木目の味わい深さも引き出せました。あまり使わないと思って200mlの容量を購入しましたが、気に入って、他の家具にも多用してしまいすぐに使い切ってしまいました。使う頻度が多いとわかっていれば1L~の容量で購入することをおすすめします。
◆作業レポート
今後の活動に生かしていくための振り返り
コメント(よかったことなど)
―『作製背景について』
作業関連の小物が増えたこともあり、元々ツールワゴンを作製予定だった矢先にプリンターを購入したため今回「ツールワゴン風プリンター台」をつくる経緯に至った
―『組み手をやってみて』
今までよりも丈夫な手法を調べたところ”組み手”という方法を知り実践した。
本来なら綿密な設計のもとノミなどの道具を使い、技術を駆使して作業する必要があった。
しかし、その技術も全くなかったため”組み手もどき”ということで挑戦した
完成後の評価として、丈夫な仕上がりではあったが、加工した寸法が少しでも合っていないとガタつきが生じる
最終的にはヤスリなどで微調整しながら、完成までたどり着いたがまだまだ経験していく必要性を感じた
―『配色のこだわり』
これまでのDIYでは単調になりがちだっただめ、今回は3色を使い分けて塗装した
天板にはローズの水性ウレタンニスを使うことで品のある印象を持たせた
中段・下段の棚板はオイルで仕上げ、ツールボックスなどを置いても馴染むように意識した
フレームにはツヤなしブラックを使用し、天板と棚板の色味を引き立たせるようにした
改善・反省点
- 全体的にネジ締めした部分が目立っている
⇒ダボやパテを使い修正可能 - プリンター関連の収納が不足
⇒天板裏側に棚を追加する
後日追加済み


