
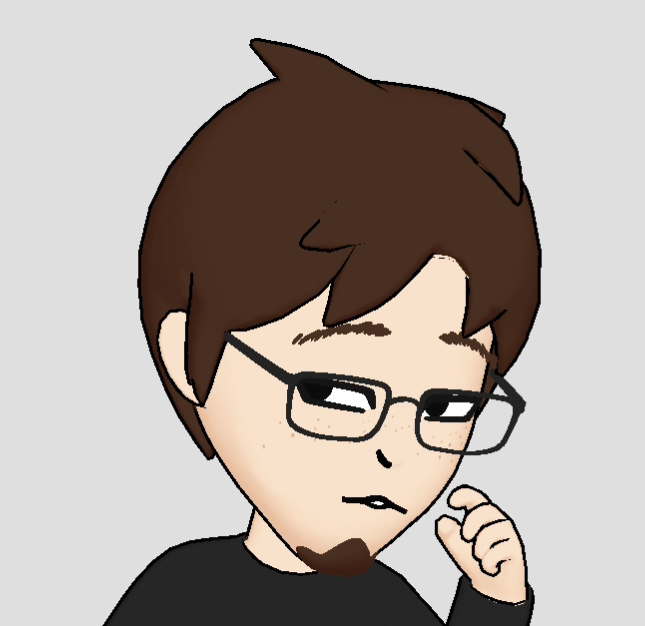
卓上サイズの収納BOXが欲しい
自分が欲しいものが売ってない
ということで
自分がお気に入りになる丁度いいサイズの収納BOX・ラックを作ってみました!
ドンッ!

✓杉材を使った暖かみのある印象
✓クラフトツールを収納が目的
作業ポイント
✔カウンターテーブルに丁度いいサイズ
✔杉材を使った暖かみのある印象
✔クラフトツールを収納が目的
今回作る収納BOXは、
プラモデル作製時に使うツール・備品などを収納の専用として作りました。
◆完成写真

テーブルの横で丁度収まりがいい感じ♪


マーカーペンなどスティック系のサイズを収納
つまみ部分があるのでそこを引っ張って取り出します。

こういう小さい引き出しがあるとなにかと便利(^-^;
100円均で購入した取っ手もバッチリ!

見た目だけで言えばイメージ通りに出来たので満足
作った感想
- コンパクトだけどしっかり存在感のある出来栄えになった!
- 杉材をワックスで仕上げたことで柔らかい木目に仕上がって印象◎
- 収納するアイテムも大体決まっていたから、小さいけど効率良く収納できる
- 100均で購入した取っ手もなかなかいい感じだった!
反省するところ
- 一つ一つの引き出しがスムーズにいかない
- 背板が付いていないためカッコ悪いし、引き出しが奥までいってしまう
作業の様子を紹介
”トリマーで溝加工をする” これを覚えた僕は ただそれを利用して引き出しなんか付けてみたい そんな気持ちが強く出ているだけの今日この頃
使用・購入品リスト
- 杉材 100×600×20mm
- クラフト用角材 5×10×900㎜
- 取っ手(100均)
- その他端材(MDF材、桐集成材など)の活用
作製費 約1000円
手順1.材料をノコギリでカットする
今回はノコギリで全てカットしました。

※上の写真は『ガンプラ塗料の専用スペース』の材料含んでいます。
僕の場合だけど、
丸ノコ使うとなるとちょっとだけ準備が手間なんだよね(>_<)
だから、これくらいの加工なら、ノコギリ一本でサクッと終わらせてしまいたいね。

コギリを使いこなせた方が作業効率がいい時あるよね
「あー作業場がほしい」
手順2.トリマーで溝加工する
トリマーを購入してまだ使いこなせるほどではないけど、
便利でめちゃめちゃ好きです。
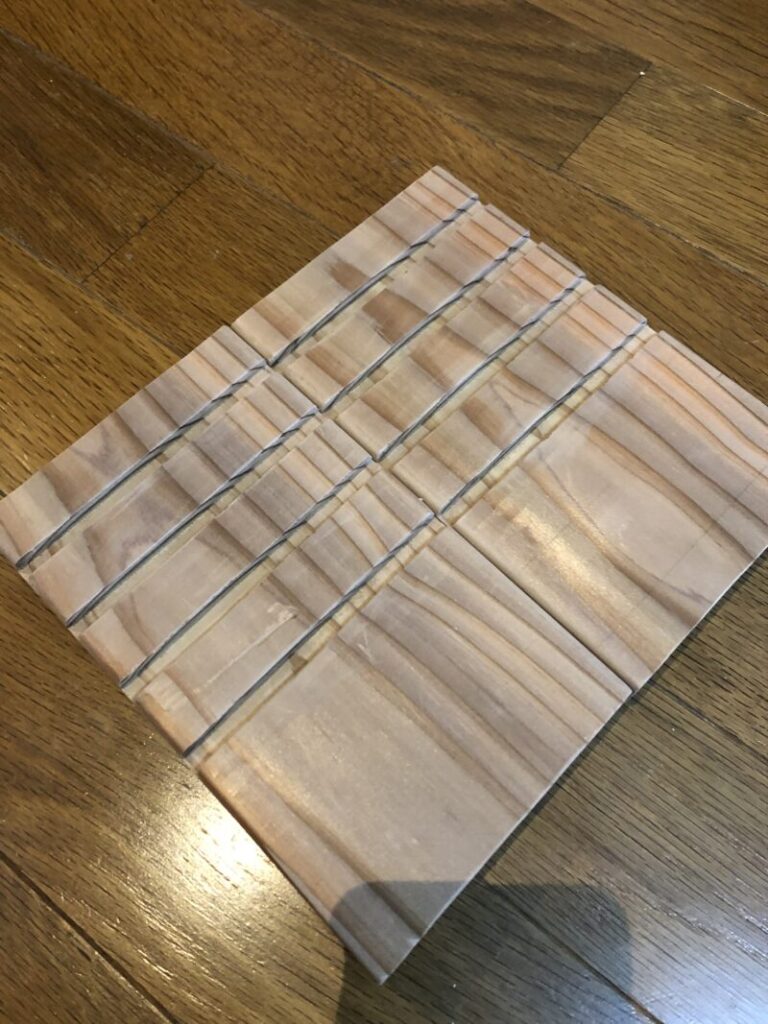
まだまだ不慣れだけど、こんな感じの溝加工はできました。
しかし、トリマーガイドに少し細工しないと作業がスムーズにいかないんですよね。
一応下の写真が細工してみたやつ↓↓


このようにして、
角材を強力な両面テープを使ってスライドさせる部分に取り付けました。
本当だったら、ガイドに穴をあけてから角材をビス止めしなければならないらしい・・・
だけど、両面テープでも一応大丈夫でした。
トリマー使って、天板にもR加工をしました。
手順3.ダボ用の穴あけ加工をする
「マーカー」というアイテムを始めて使いました。
そういえば、
ダボを使って組み立てしたことがありませんでした。
こんな便利アイテムがあるなんて知らなかった。
これがなかったら、多分今回の作品は失敗だったと思う。
DIYをする人はみんな知ってるんだろうけど、
僕は知らなかった!
以下、使い方↓
①ダボ穴に「マーカー」を挿し込む
使用したダボはΦ6
前もってドリル加工したΦ6の穴にマーカーを挿し込んで使用します。

②組み合わせる材料を押し付ける
これで反対側のダボ穴の位置が決まってしまうので、
自分が設計した位置とズレがないように慎重に合わせます。
そしたら、少し押し付けます。

③印が付いたところにダボ穴を加工する
マーカーから材料を離してみると、
”ちょん”という跡が残る。
その位置でもう一度ドリル加工を行います。

以上、マーカーの使い方でした。
手順4.組み立てる
組み立ては一切釘を使用せずに全てダボのみで組み立てました。

普段はネジで固定してるから、
ダボだけだとちょっと強度が心配だったんですよね(^-^;
でも、木工用ボンドも一緒に使ったし、
心配だったグラつきなどは一切感じられませんでした!
屋内用の小物DIYなら「ダボ+接着剤」でも十分実用的だし、作業が楽ちん!
手順5.『vintagewax』で仕上げる
「長く使いたい」
「木の風味を出したい」
ワックス仕上げってやっぱこれだね
ワックスって乾燥に時間かかるし手間もかかるから、
普段のDIYでは避けてきてるんだけど
木の風味を出したい!
メンテナスして長く使いたい!
みたいな家具はワックスで仕上げておきたいんだよね。

手順6.ミニ引き出しを作製する
あればなにかと便利だし、あればちょっとオシャレじゃん?

<ミニ引き出しの作製手順>
①BOXで使うMDF材と角材を接着剤で固定
②化粧板を接着剤で張り付ける
③お気に入りの取っ手をつける
ビス止め無し!

手順7.4段の簡易式薄型引き出しを作製する
ペンやヤスリなどスティック形状のツール専用の収納です。
作った流れはこんな感じ↓↓

<使用材料>
・MDF材
・割り箸(適当な長さにカット)
・丸棒をカットしたもの

接着剤で固定する
ちなみに丸棒の役割は、
引っ張るためのつまみ部分

こんな感じでつまんで引き出すタイプです。
手順8.目隠し用カバー作製する
これがあるのとないのとでは、
かなり印象が違う。

<使用したもの>
・5×10のクラフト角材
・ベニヤ板端材
ベニヤ板端材にカットしたクラフト材を接着剤で張り付けただけの手抜き作業。
まあ、そんなもんでしょ。
◎塗料:水性オイルステイン(ダークウォルナット)


なぐり書きメモ(自分に向けて)
メモ帳に記入するのがめんどくさい。
だからここによかったこととか反省点を自分が振り返るためのメモとして残しています。
よかったところ
『ワックス仕上げ大正解』
何色で塗装するか、ウレタンニスにするかなどかなり迷った。
色もそうだが、仕上げ塗料の種類にも頭を悩ませた。
普段の手入れとしてホコリなど拭き取れるようにウレタンニスを考えたが、ツヤがあるとなんとなく深みがなくて完成イメージと遠くなる。
ただの水性塗料だと水分の汚れなどに弱いし、拭き取るようなメンテナンスは望ましくない。
ちょっと作業が手間だがワックスを使って、着色仕上げをすることでどちらの問題も解消できる。
さらに仕上がりがすごく自然で重厚感に近い印象になった
『つまむタイプの取っ手』
”指が入るスペースが狭くて引手を付けられない”
作業中にこんな問題点が発覚する。
引手なしでも使えないこともなかったが、使い勝手が悪そうであることが想像できた。
そもそも、この辺の詳細設計、プランのようなものはいつもその場しのぎのようなことが多い。
最終的に余っていた丸棒をカットして、ホビーカンナで平らな部分を作って接着剤で取り付けてつまめるようにした。
これがなかなかよかった。
この方法は今後の作品でも応用できそう。
改善点・反省点
- トリマーの取り扱いがまだまだ不慣れ。
そのためトリムの仕上がりが汚い部分が少々発生 - MDF材が未塗装のためそこだけ浮いて見える印象
⇒MDF材の塗装方法を調査し、必要に応じて施工していく
